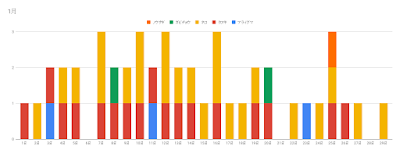タヌキーアライグマと愉快?な仲間たち編

身近な動物でアライグマとも混同されやすい動物の一つとして、タヌキの生態や特徴を紹介します。写真は全てホンドタヌキです。 記事作成日: 2019.04.27/記事更新日: 2021.04.19 日本古来の動物 ホンドタヌキ (かみね動物園) ・夜行性 ・都心から田舎まで神出鬼没! ・家族思い? ・実は木登りもちょっと出来る ・何でも食べる雑食性 ・家は賃貸派 ・欧州ではアライグマと同じく外来種 特徴を簡単に上げると以上になります。一つづつ見ていく前に、概要をおさらいしましょう。 冬毛のタヌキの横顔 タヌキはイヌ科の中型動物です。大きさとしてはネコより気持ち大きいぐらいですが、外見はおおよそ同じくらいです。体重は3~5kg程度と軽いです。丸い顔の印象ですが、横からみるキリっとしていてイヌ科の動物らしさを感じます。 日本では沖縄を除き生息します。海外ではベトナムからロシアにかけて沿岸部側に生息しているほか、外来種として毛皮用にロシアから持ち込まれた個体が東ヨーロッパを中心に生息し、生息を拡大しています。 日本では様々な場所に生息し相当数生息していますが、IUCNのRED LISTを見ると東アジアでの生息数は不明な部分が多いようです。一方で外来種としてはフィンランドなどに相当数生息してるのが紹介されています。 日本のタヌキは亜種という細かい区分で分類した場合、北海道に住むエゾタヌキとそれ以外の本州などに住むホンドタヌキに分類できます。基本的には同じ様な生態や特徴を持ちますが、エゾタヌキのほうが少し体が大きく毛足が長く寒冷地に対応できるようになっています。恒温動物の同じ種や似た種では寒いほうが体が大きくなる典型的なベルクマンの法則に当てはまるタイプです。 冬眠する生き物ではありません。春先に子供を産み、秋には育ちます。そして秋には冬へ向けて脂肪を蓄え、冬眠せず冬を乗り切ります。私の観察でも、タヌキは冬にも行動する姿を確認しています。一方で寒さのより厳しいエゾタヌキは冬眠はしないものの冬の行動をかなり抑えます。アライグマやアナグマも寒さの厳しさで行動が変わるので、タヌキも似たような生態を持つのだと思います。 夏毛のホンドタヌキ (夕方の写真で色味が黒っぽくなっています) 上の写真と同じタヌキ 冬毛と夏毛があり、冬はモコ...